
江沼郁弥
2017年9月にplentyを解散して以降、1年はまるっきり音沙汰なしだったかと思えば、1年経った2018年9月にいきなりリキッドルームでワンマンライブを開催し、そこからはアルバムをリリースしたり、バンド編成でライブを行ったり、シングルの連続リリースを敢行したり……とソロ活動を展開してきた江沼郁弥。そのセカンドアルバム『それは流線型』は、ライブのサポートもしている木のメンバーたちとの共同作業を通して作られ、前作『♯1』とはまったく違う様相をもった作品となった。この機会に、彼にとってこのソロプロジェクトはどんな意味をもっているのか、このアルバムで彼が求めた「社会性」とは何か……気になっていたあれこれを語ってもらった。
そのアルバムを引っさげて開催されるリリースツアー、ファイナルのリキッドルーム公演も必見だ。
ファーストは、自分が今も楽しみながら音楽を作れているかの確認作業だった
――plentyが解散して、しばらく音沙汰がないなと思っていたら、いきなりライブをやって(2019年9月8日、リキッドルーム)、そこでソロアルバムのリリースが発表されるという。傍から見てると唐突に始まった感じがあったんですけど、本人としてはどういう流れだったんですか?
江沼:plentyを解散してから、特にリリースする予定もなかったんですけど、制作だけはずっとしてたんです。それで半年くらい経って曲も溜まってきたから、何かしらの形で出したいなと思って、今の事務所の人に「こういうのがあるんですけど」って話して……という流れだったんです。そのときはライブも全くやる予定なかったんですよ。ライブが嫌いとかじゃなくて、そんな活動的にやっていくつもりは本当になくて、もっと自由に好き勝手やって、やってはまたいなくなったりとか、そういうイメージをしてたんですけど……ファーストアルバムを作ってるときに、鍵盤のオヤイヅカナルという子と会って。素晴らしいなと思っていたら、彼がバンドを組んだというんで、そのバンド(木)のライブを観に行ったんですよ。それがすごくて、感動して。この子たちとやりたい、この子たちにサポートしてもらったらライブめちゃくちゃおもしろいんじゃないかなと思って、ワクワクして。それで結局、リリースよりライブのほうが先になったっていう。
――オヤイヅくん、木と出会うことで、ライブでやるイメージが生まれたんだ。
江沼:そうですね。ファーストを作っているときは、そんなにフィジカル的なイメージがなくて。主張がなく、静けさがあって淡々としているみたいな。自分が今も楽しみながら音楽を作れているかの確認作業みたいな感じで作っていたから、ライブでそれを聴かせて「どうですか」みたいなことは考えていなかったんですよ。でもその子達と会って「ライブってすげえな」と思って。で、すぐ声をかけたんです。
――木の何が、江沼くんにそんなに響いたんですか?
江沼:なんかすごく自由だったし、迫力があったんですよ。最初に観たときは下北沢251のステージじゃなくてフロアでライブしていたんですよ。音もクソもないような感じなのに迫力があって。曲もすごく説得力があるというか。何て言うんだろうな、自分にないものを持ってる感じがしたんですよね。人の顔色を伺わないで音楽してる感じっていうか。バンドをやってたときとか、疑う瞬間もたくさんあったし、「どうすか?」っていうシーンもいっぱいあって、そういのに疲れてたっていうのもあるところで、そうじゃない音楽のありかたを体現している感じがして。全員自分より年下だし、すげえなって。

責任みたいなものは感じていないですけど、変な迷いがなくなってきたかもしれない
――なるほどね。ライブをやって、アルバムをリリースして、それから1年近くが経っているんですけど、そのあいだ、意外とコンスタントに活動していますよね。
江沼:そうなんですよね。だから、このあと少し休みます(笑)。とりあえず1年、お試し期間っていうほど気軽なものではないですけど、その1年の中に、最初3人編成でのライブがあって、途中4人になって、シングルをリリースして……いろいろな変化があったんですよね。だから結果的にコンスタントになったというか。3人だったら3人で曲をアレンジしてライブもレコーディングもしたいし、4人になったらなったでそれでやってみたいしっていうので、ライブもリリースも増えて。
――じゃあ、ひたすら一本道を歩いていた感じでもないんだ。
江沼:まあ、でっかい意味では一本道ですけど、どんどん人を入れて変化していこうという。自分が思い描いているものとはズレてはいないけど、1個のことを忠実にやっていくという感じでもないですね。
――ひとりでファーストアルバムの曲を作ってたときとはだいぶ違うところに来ている感じもしますよね。
江沼:そうですね。まあ、当然っちゃ当然なのかなって感じもする。ライブやってお客さんに会って。みんな喜んでくれるみたいなこともあって。責任みたいなものは感じていないですけど、変な迷いがなくなってきたかもしれないです。歌うのか歌わないのか、みたいな悩みは動き出したら取れてきましたね。動く前はやっぱり……plentyを求めてる人に出くわすことになるから。その人たちを説得する術が、まず観てもらうしかないっていうか。それでも言う人は言うし、付いてきてくれる人は付いてきてくれる、それだけなんだけど、そこに臆病になってたから。でもそれがもう、いい意味でどうでもよくなったし、もっと自信が出てきたし。インストなのか歌うのか、みたいなこともはっきり分かれてきたというか、脳みそのなかが整理されてシンプルになった感じはしますね。
なんかね、受け身じゃなくなったんですよ、ソロを始めて
――ファーストは文字通りひとりでイメージの中で作り上げた世界という感じがしたけど、今回のアルバムはすごく実体があるというか、肉体があるなって思うんですね。ファーストのときはどこか仙人っぽかったもんね。
江沼:ま、そういう生活もしてましたし(笑)。何歌おうとか、何をテーマにとか、ほんとはそんなに難しく考える必要はないのに、考えちゃってましたね。別に等身大のものを目指しているわけではないけど、余計なことは考えず、好きか嫌いかでジャッジして、それが好きな人を増やしていくだけですからね。
――作り方自体もファーストと今回はだいぶ違いますよね。
江沼:ファーストのときはほんとにひとりと、カナルくんのサポートで作っていたんですけど、今回は元のデモを作って、ライブでもサポートしてくれている3人に投げてるんですよ。骨組みがあって、それを3人にアレンジしてもらって、それをまた切って貼ってっていう。2回アレンジしているみたいな感じなんですよ。なんていうか、ひとりリミックスみたいな感覚。1個フィルターというか手間が増えているというか。前は純粋な、ぼやぼやっとした卵みたいなものを出した感じなんですけど、今回はそれを磨き上げるというか、ぶつけて角を取っていくというか。そういう感覚ですかね。
――投げてアレンジしてもらうというところはバンドっぽいけど、それをもう一度自分の形に磨き直すみたいな。
江沼:うん。自由な感じもあるし、自由じゃない感じもあるし。バンドのときみたいに任せっきりって感じではもちろんないし、コントロールの中で不意に出てきたものをキャッチしていくっていうか。
――その自由であると同時に不自由であるっていうことが大事なのかもしれないですね。サポートメンバーではあるけれど他者と曲を作って、でもそれを最終的には自分のコントロール化で作品化していく、バンド的だけどバンドではないっていうのが。
江沼:居心地いいですよね。責任みたいなものからは解放されているから。バンドのメンバーだったら、レコーディングとかも多少は「許していく」作業が必要なんですよね。もちろんネガティブな面だけではないけど、そういうものが付きまとっていたんですけど、今は許さなくていいから。ダメだったらダメだし、やりたくなかったらやらなくていいし。納得したところで終われるというか。
――でも、徹底的にひとりの世界で作ったようなファーストの気持ちよさもあるじゃないですか。そうじゃなくて、結局人と一緒に音を作るっていうところに戻ってきたのはどうしてなんでしょうね?
江沼:なんかね、受け身じゃなくなったんですよ、ソロを始めて。PAさんとか照明さんも、自分がやりたい人を自分で声かけて引っ張ってきてるんですよ。その感じなんですよね。だから次の作品を作りたいなってなったときに、あいつらとやりたいなって思って声をかけたっていう。曲によってハマる人をチョイスしてやってる感じ。人とやるっていうよりも、その曲に対して誰がいいかっていう考え方なんですよね。それが今回にかんしてはライブのメンバー内でやりたいなと思ったっていう。だから次はそうじゃないかもしれないし。今はスタジオで録らないっていう前提でやっているけど、スタジオで録るかもしれないし。

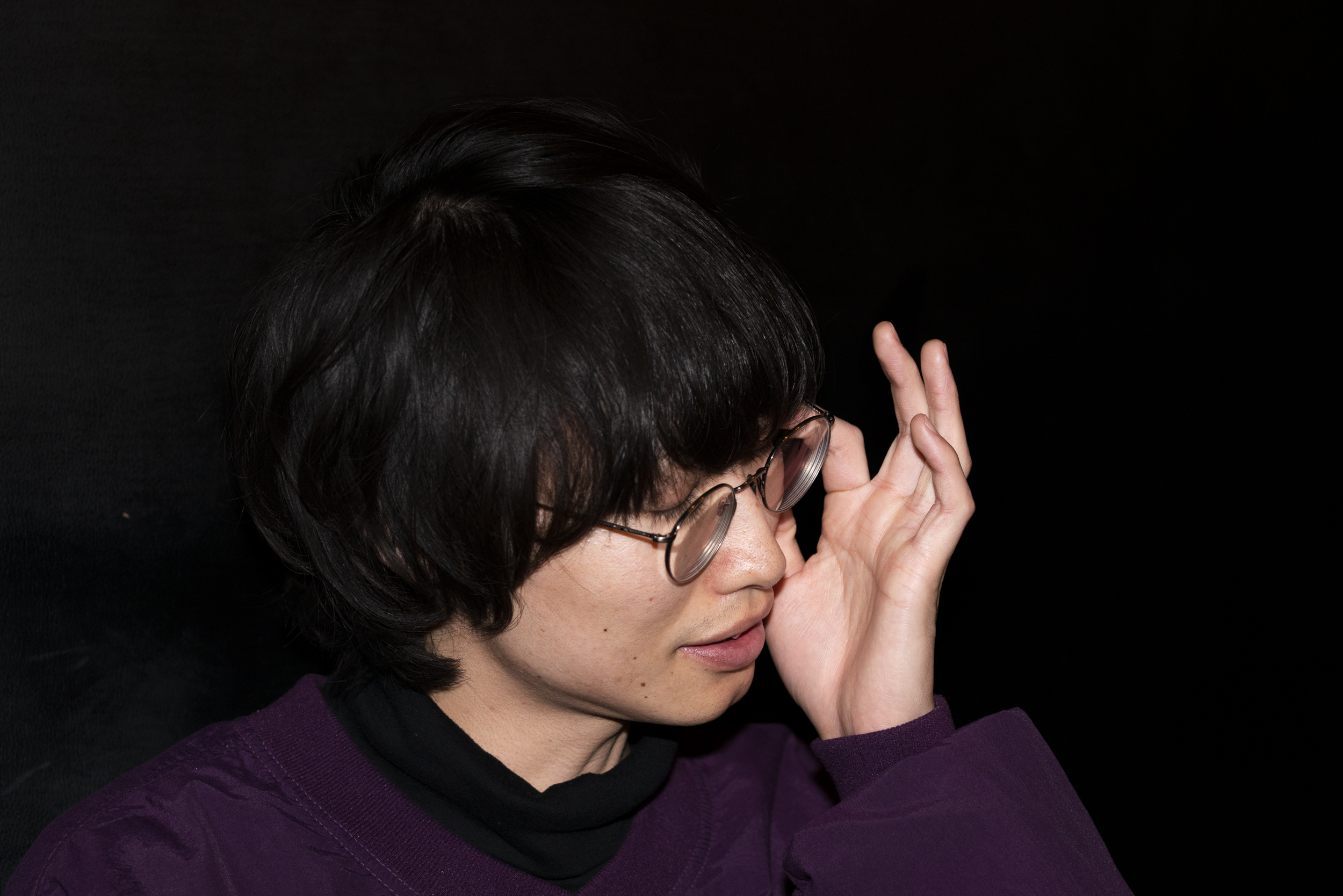
セカンドは、作品に社会性があるというか。今生きている人の言葉が歌いたかった
――なるほど。今回、サウンドとしてはどういうものを目指していたんですか?
江沼:今回のアルバムはファーストに比べたら音のレイヤーの数が少ないんですよ。最近は音が少ない、わりと隙間のある音楽が流行っていて、そういうところも意識してはいたんですけど、それだとなんかちょっと面白くないかなっていうのもあって、隙間もすごい意識したけど隙間が多すぎない感じというか。特にベースですかね。それをベースがどう行くかっていうところですごく考えていましたね。メロと歌がいちばん大事だっていうのが大前提としてありながらも、それと並行して低音がどう走っているかというのはすごく意識しました。ファーストは埋まっている感じ、低音がグワーッと来る感じでしたけど、それとは違う――。
――うん、みっちり隙間を埋めている低音というより、楽器感があるというか、弾いている感がありますよね。
江沼:それが欲しかった。セカンドは、作品に社会性があるというか。社会と関係ないファーストを作ったから、セカンドは今生きている人が作ったもの……今生きている人の言葉っていうか、そういうものが歌いたかったから。
――「社会性」が欲しかったんですか?
江沼:なんだろ、今も事務所には所属してますけど、ひとりでやるようになって社会に触れる機会が増えたんですよ。そこで……全然直ってないけど、言葉遣いとか、そういうものに触れてこなかったんですよね、俺は。守られてたから。でもそうじゃなくて、自分で人に会って「一緒にやりませんか」って声をかけるとか、そこでいろんな話を聞くとか、生命保険に入るとか、わかんないけど(笑)。なんか、俯瞰できるようになった感じがするんです。それで、それを浮かび上がらせたい、現代を模写したいというアイディアが生まれたんですよね。
――「模写」というのがおもしろいですよね。確かに今作の歌詞には社会というか他者がいっぱい出てくるんですけど、そこに対してメッセージしたり敵対したり迎合したりするんじゃなくて、ただその一員として「いる」っていう。
江沼:そういうふうに見えてるっていう。冷めてるというとあれだけど、世の中見て「終わってるな」と思うときもあるし、「まだ終わってないのかな」ってときもあるし。それがいい悪いじゃなくて、そういう感じなんですよね。そのなかでどうするかっていう。
――「見えてる」ままを書いているというのは、つまりちょうどよく中和させようとしていないというか、要するに「俺にはこう見えてるんだけど、どう?」っていう問いを突きつけているという言い方もできますよね。それは江沼くんの言う「社会」との一種のコミュニケーションだと思います。
江沼:うん。自分はそれが好きだし、それが好きっていう人がどれぐらいいるのかなって。でもそこに至るまでは「自分が間違ってないってどうして思えるんだろう」って……今はこれでいいって思えているからこうやって話せているけど、不安でした。それをセカンドを作り終えたことで取り除けて、こういうモードになれたっていう。ずっと、どこに行っても居場所がないなと感じていながら音楽をやってきた気もするけど、今は居場所がないなら自分で作ろうと思ってやっていますね。

――もうすぐリリースツアーもありますが、ライブもより開けたものになっていくんですかね。
江沼:作品は作品で気に入ったものができたので、それはそれで聴いてほしいけど、ライブは全然別と思っていいかもしれないです。おもしろいです。すごくいいと思うので、目撃者になってもらえたらいいなと思います。
–
11月30日公演〈ワンマンツアー2019冬〉の詳細はコチラをチェック!









